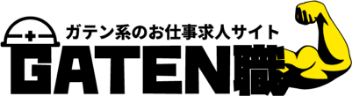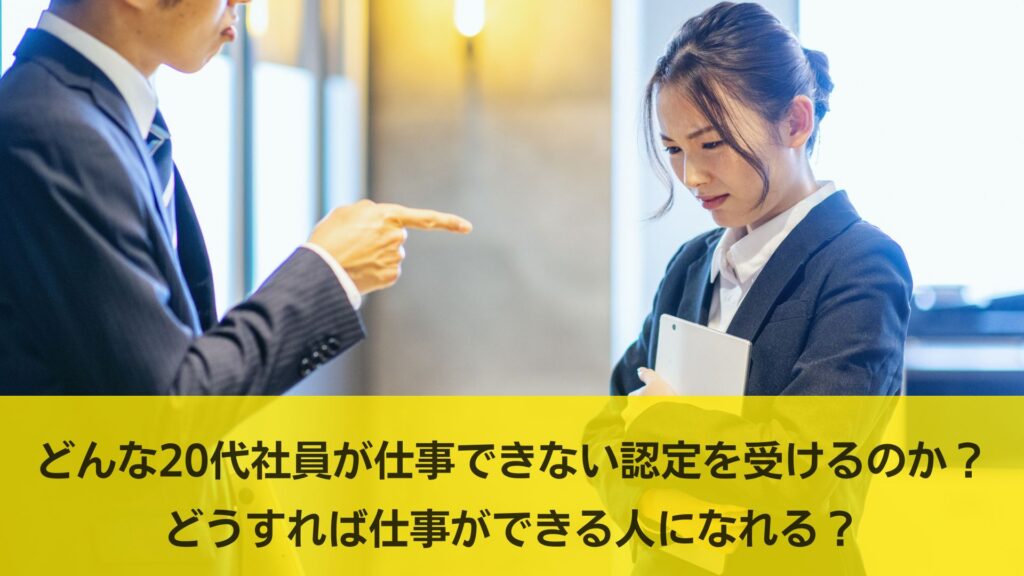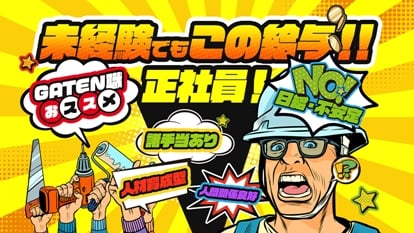マイナビ転職の来訪者を対象としたインターネット調査※によると、20代の68.6%が「自身の仕事に自信がない」と回答しています。
※調査期間2021年7月8日~7月12日、回答数1,351名
仕事ができないことに悩む20代は多いです。
「周りの足を引っ張っていると感じて辛い」「日に日に社内での立場が悪くなっている。もう仕事を辞めたい」と苦しんでいる人も少なくありません。
今回は「仕事ができない…」と悩める20代のために、なぜ仕事ができないと思われてしまうのか、どうすれば仕事ができるようになるのか解説します。
- 自分の弱みを把握する
- 失敗したら再発防止策を考える
- 約束は守って信用を積み重ねる
- インプットとアウトプットが大事
どんな20代が仕事できないと思われるのか
まずは、どんな20代が「仕事できない認定」を食らうのか。
仕事できないとされる人の特徴から知っておきましょう。
そしてできれば、この「仕事できない人像」に触れないようにしておきたいところです…。
人の話を聞かない
コミュニケーションの基本中の基本、「相手の話を聞く」ができない人は、「仕事ができない」とみなされても仕方ありません。
話しててもどこか上の空。
そうなると当然意見を求めても的はずれな意見しか出てきません。
これでは「仕事ができない」と思われても仕方ないですよね。
時間・約束を守らない
時間と約束を守れない人は、その約束した相手に悪い印象を与えます。
それが仕事上の約束だったなら、仕事に支障をきたすわけですから、「あいつに仕事をまわすのをやめよう」と思われても仕方ないことです。
考えに柔軟性がない
言ったことをきちんと守る人は多いですが、「言った以上のこと」をやる人は少ないです。
もっと柔軟に、どんな状況下でもきちんと対応できる人が「仕事のできる人」です。
指示待ち人間
「次何をすればいいか」を自分で考えられない人は「仕事ができない人」ですね…。
上司の指示がないと何もできないなら、会社にとってお荷物です。
そんな人は、そのうち高精度のAIに仕事を取って代わられるかもしれません。
間違いを正さない
誰しも失敗、間違いはあります。
問題は、その間違いを間違いのままにしている人です。
間違ったなら、「どうして間違ったのか」「どうすれば今後の間違いを防げるか」を考えられる人が「仕事のできる人」なのです。
チャレンジしない
決まったこと仕事ばかりしている人、新しい分野の仕事にチャレンジしない人も「仕事のできない人」とみなされがちです。
チャレンジするためには、様々な前準備が必要です。
その前準備も含めてすべてこなせる人が「仕事のできる人」なのです。
手っ取り早くチャレンジするしかない局面に追い込むために、「転職」という選択肢もあります。
20代の利用にうってつけな転職サイト・エージェントを活用して転職してみるのも、一つの手です。
20代におすすめの転職サイト・転職エージェント
20代におすすめの転職サイト・転職エージェントをまとめます!
具体的には以下の通りです。
- ハタラクティブ
- doda
- マイナビエージェント
これらについてそれぞれ解説します。
ハタラクティブ
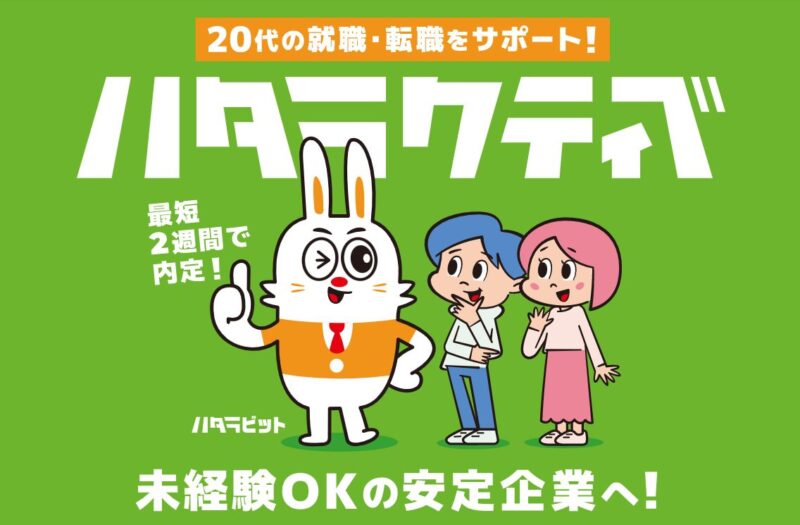
ハタラクティブの特徴
- 経歴に自信がなくても転職成功できる
- アドバイザーのサポートが手厚い
- LINEでのカウンセリングが可能
ハタラクティブは、フリーターや既卒、第二新卒など、若年層向けの就職支援サービスです。
未経験者向けの求人が豊富で、丁寧なサポートで就職成功率は80%以上と非常に高いです。
またハタラクティブは、未経験者向けの求人が豊富です。
そのため、職歴に不安がある方でも、希望の仕事を見つけることができます。
それ以外にも履歴書や面接対策はもちろん、キャリアカウンセリングや転職活動のアドバイスなども対応してくれます!
転職活動に不安がある方でも、安心して利用することができますね。
ぜひハタラクティブを検討してみてくださいね。
doda

| 求人数 | 約260,000件 |
|---|---|
| 対応地域 | 全国47都道府県 |
| 料金 | 無料 |
| 公式サイト | https://doda.jp/ |
| 運営会社 | パーソルキャリア株式会社 |
dodaは、転職を考えている方におすすめの転職サイトです。
dodaは、求人数が豊富で、希望の条件に合った求人を簡単に見つけられます!
また転職のプロであるキャリアアドバイザーが無料でサポートしてくれるので、転職活動を効率的に進めることができます。
さらにdodaでは、転職に必要な書類の作成や面接対策などのサポートも充実しています。
転職を考えている方は、ぜひdodaを検討してみてください。
マイナビエージェント

マイナビエージェントの特徴
- キャリアアドバイザーが丁寧にサポートしてくれる
- 非公開求人が多い
- サービスが充実している
- 20代など若者の転職に強い
マイナビエージェントは、転職を考えている方におすすめの転職エージェントです。
20代向けの求人数が豊富で、希望の条件に合った求人を簡単に見つけることができます。
また、転職のプロであるキャリアアドバイザーが無料でサポートしてくれるので、転職活動を効率的に進めることができます。
他にも転職に必要な書類の作成や面接対策などのサポートも充実しています。
転職を考えている方は、ぜひマイナビエージェントを検討してみてください。
あなたが自分を仕事できないと思う理由
さて、ではここからは、あなた個人の話をはじめましょう。
「仕事ができない」ことを日々嘆きながら、毎日床につくあなた。
どうして「仕事ができない」と思うに至るのか。その原因から探っていきましょう。
自分の短所がはっきりしてないから
まずあなたは、自分のことがあまりわかっていません。
自分はどこに弱点があって、何の分野が苦手なのか。
そういった自分の短所が理解できないから、間違った行動を起こしてしまうのです。
「失敗」を「失敗のまま」で終わらせてるから
仕事のなかで失敗したとしたら、それを失敗したな、で終わらせてるのではないですか?
失敗したなら、しっかりと再発防止策を考えてください。
どうすれば「仕事できない」を脱却できるか
どうすればこれからは「仕事ができない」ではなく「仕事ができる」認定を受けるにつながるのか。
これからは、かつての自分に向けられていた「悪い印象」を覆すことができるか。
仕事できない認定を脱却するための方法を、一緒に探していきましょう。
約束を守る
時間や約束をしっかり守ることで、上司や同僚から信頼を集めることができます。
信頼が厚い人=仕事ができる人という評価に繋がりやすくなります。
「約束したことはちゃんとこなす」
簡単ですが、その効果は大きいです。
インプットとアウトプットを欠かさない
何も考えないまま、日々の仕事をこなしているだけでは、まったく進歩しません。
新しい分野のしごとにチャレンジするためにも、日々のインプット、そしてアウトプットも欠かさないようにしたいです。
時間が許すなら、セミナーに顔を出して、そして得た知識を仕事に活かす…。
これができれば、仕事の能率が上がり、「仕事ができる」という認定を受けやすくなるはずです。
まとめ
自分は仕事ができないと嘆いているあなた。
あなたがその評価を覆すためには、どうして自分の仕事能率が低いのか、どうして他人から仕事ができないと思われるのか。
しっかりとその要因を探るところから始める必要があります。
そしてその要因がわかったなら、あなたの知識と経験を活かして、仕事ができないと思われる要因をなくすためのアプローチする必要があるのです。
今回の記事を参考に、これからは「あいつは仕事できる」と思われる働きぶりをみせてください。