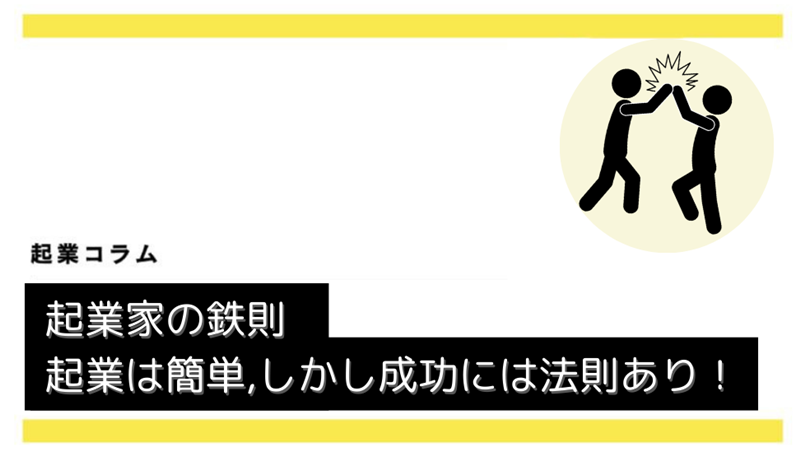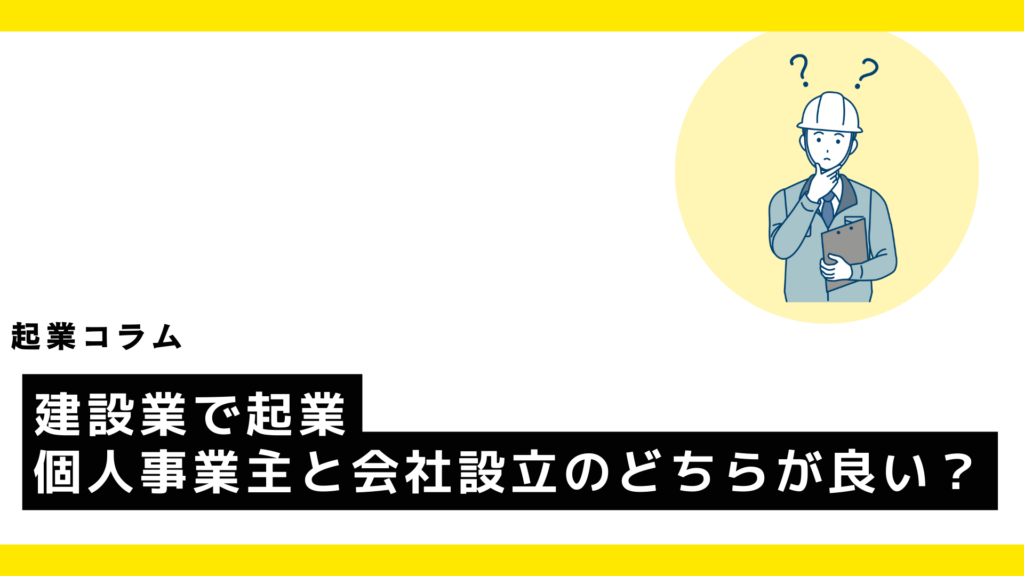起業『参入』しやすい業種と
起業『成功』しやすい条件を知り
成功する起業家への道を確実に歩もう。

やりたい事をやろう!でもやってはいけない事を知っておこう。
起業参入しやすい業種にはリスクが多い
『参入』しやすい業種と『成功』しやすい業種は別物です。
『参入』しやすい業種には下記のリスクがある事を忘れてはいけません。
起業『参入』しやすい ≠ 『成功』しやすい のではありません。
起業『参入』しやすい →→ 競争が激しい →→ 差別化しにくい・価格競争に陥りやすい

起業参入しやすい業種とは?
起業を考える際、まず頭に浮かぶのは「どんな業種で起業しよう?」という疑問でしょう。
一般的に、起業しやすい業種として下記がよく言われます。
起業した場合の長所と短所を挙げてみました。
飲食店
カフェ・レストラン・バー・居酒屋…
- 長所
- 初期投資の低く抑える事もできる: 小規模なカフェやフードトラックなどウーバーイーツの組込で少ない資金で始められる事もできる
- 安定した需要: 地域に根差したローカルな飲食店は、顧客のリピーター化が期待できる
- 自由度: メニューやサービス内容を自由に設定でき、自分の創造力を発揮する場が多数ある
- 短所
- 利益率が低い: 飲食店の利益率は一般的に低く、薄利多売となる
- 人件費がかかる: 食材費や賃料などのコストに加え、人件費も大きな負担となる
- 営業時間長い: 労働時間の長く、人材確保も難しい
- 顧客の嗜好の変化: 顧客の嗜好は常に変化しており、対応できないと売上減少
美容関連
ネイルショップ・マッサージ・エクステ…(美容院は除外)
- 長所
- 高い顧客忠誠度: 一度満足した顧客は長期間にわたってリピーターになりやすいです。定期的なメンテナンスが必要なため、一度の成功が長く続く関係を生むことができる
- パーソナライズしたサービス: 顧客一人ひとりに合ったサービスを提供できる
- 多様なビジネス展開: サービスの種類や販売する商品など、多岐にわたる分野でビジネスを展開できる
- 短所
- 新規顧客獲得の難しさ: 新規顧客を獲得することが難しく、既存顧客の維持の負荷が高い
- 技術力の競争: 技術力が高い人材を確保しなければ、競合店と差別化できない
- 設備投資: スペースや衛生設備など、必要な設備投資が必要
- 景気の影響を受けやすい: 景気が悪化すると、美容関連への支出は減少する
IT関連
ウェブデザイナー・プログラマー・システムエンジニア…
長所
- 高い需要: デジタル化が進む現代において、ITスキルへの需要はますます高まっています。ウェブ開発、アプリ開発、ITコンサルティングなど、多くの分野での活躍できる
- 場所を選ばない: インターネットがあれば、どこにいても仕事ができ、リモートワークやフリーランスとしての自由な働き方が可能
- スケーラビリティ: ビジネスが成長しやすく、スキルの向上に従って大規模なプロジェクトにも挑戦できる
短所
- 新技術革新のスピードが速い: AIの登場で代替される分野が増加する傾向で、さらに最新技術を学ぶ必要がある
- 競争が激しい: 競争が激しく、常に新しいアイデアを生み出す必要がある
- 人材確保: 優秀なエンジニアやプログラマーなどの確保が難しい
起業 成功 しやすい条件とは?
一般的に、起業家として成功する条件は下記と言われます
- 初期費用が低い
- 需要が安定している
- 利益率が高い
- リピーターが多い
- 場所がいらない
これらについてそれぞれ解説します。

初期費用が低い
初期費用を低く抑えられるかは、スタートアップ時に非常に大切な事です。
起業時はともすると舞い上がってしまって、必要以上に過度な設備投資をしてしまうケースが見られます。
特に店舗を構える事は多い飲食店やネイル・マッサージ店などでは注意が必要です。
飲食店であれば、キッチンカーやウーバーイーツなどを組み込んだプラン、ネイル・マッサージでは訪問サービスから開始する事も有効な手段です
需要が安定している
このブログでも書きましたが、一過性のブームに乗っているだけの需要では、必ず廃業・倒産の憂き目にあいます。
ブームや流行に乗っていいのは、鋭敏な情報収集ができ、流行やブームを作り出せる程の大量の資本を一気呵成に投入できる場合のみです。
記憶にある人も多いでしょうが、タピオカブーム等は大資本によって『作り出された』とう側面もあり、ブームが一番盛り上がる頃には十分儲けた大資本は、撤退準備を始めているのです。
利益率が高い
起業スタート時は、売上を作る為に割引き、セール等々で、値段を下げて販売する事はよくあります。
それ自体は悪い事ではありませんが、それが販売計画の中で実施されているのかが、とても重要です。
利益が薄く無理が重なると品質低下を招き、いずれ顧客離れが起こります。次項にもあるリピーターを生み出す事ができません。
リピーターが多い
事業の中心命題は、いかにリピーターを生み出すかであると言っても過言ではありません。
パレートの法則はご存知でしょうか?たった20%のリピーターが80%の売上・利益をもたらしてくれるという、一般的にビジネス上でよく語られる起業家が知っておくべき法則です
厳密に【2・8】(ニッパチ)になるかどうかは、ケースバイケースですが、旧来から常識とされる事で先人の経験則であり、一面の真実でありましょう。
それ程までにリピーターを作り、育てられるかは大切な事です。
お客様全体に平等に奉仕する事も大切ですが、20%のお客様を大切にする事はビジネスにおいて重要です。
また、どの20%を大切にするのか?の吟味をする必要があります。売上?利益?来店回数?受注回数?それぞれのビジネスに合わせた選択が大切です
場所がいらない
要は固定費となる家賃や不動産関連は極力抑える事が大事です。
IT関連の様に在宅業務が可能な場合もありますが、店舗や作業場が必須のケースもあり、全てのケースにあてはまる訳ではありませんが、それでも最小限に抑える事が重要です。
建設業界には、起業成功に最適な環境が整っている
建設業界は大手ゼネコンから地域密着型の工務店まで、様々な規模の企業が存在します。 近年では、企業の成長戦略の一環として、従業員の独立を支援する動きが活発化しています。
起業を後押し、具体的な独立支援策がある会社が多数ある
【具体的な独立支援策の例】
- 独立資金の貸付制度: 独立時に必要な資金を、低金利で貸し出す制度を設けている会社があります。
- 技術指導・経営ノウハウの提供: 独立後も、一定期間は技術的なサポートや経営に関するアドバイスを受けられる体制があります。
- 顧客の紹介: 元請け会社として、独立した会社に継続的に仕事を発注するケースもあります。
- 資格取得支援: 独立に有利な資格の取得費用を会社が負担する制度があります。
これらの支援策は、起業における大きな不安要素である「資金調達」「経営ノウハウ不足」「顧客獲得」を解消する強力な後ろ盾となります。
建設業界では多くの企業が、独立、企業を目指す従業員への支援制度を充実させています。
資金面でのサポートはもちろん、経営ノウハウの提供や顧客紹介など、独立、起業後の成功を後 押ししてくれる心強い味方となってくれるでしょう。
転職活動に『独立』や『起業』をキーワードで検索すれば、都市・地方を問わずヒットします。またほとんどの建設業種で将来の『起業』希望者は歓迎されます。
職人技術は無形の財産
建設業界は、まさに「手に職」の世界。言い方を変えると、積み重ねの世界なのです。
もちろん人によって器用・不器用の違いはあるでしょうが、現在は多くの道具が電動化されて、器用・不器用の様な先天的な能力よりも、最後まで丁寧にやりきるという人間としての粘り強さの方が大切です。
早い遅いの差はあれども、順々に専門的なスキルや知識を身につき、世界中どこでも(まさに海外でも)通用する一生モノの財産となります。
高い技術力は高収入にも直結し、安定した収入を得ながら、自分のペースで仕事を進めることも可能です。
建設業界で働くということは、現場でしか学べない専門的な知識や技術を身につけることを意味します。 確かな技術力は、あなたにとって一生ものの財産となり、独立後も強い武器となるでしょう。
- 高い専門性で差別化を図れる: 専門性の高い技術があれば、競合との差別化を図り、独自のポジションを築くことができます。
- 価格競争に巻き込まれにくい: 技術力があれば、価格ではなく品質で勝負できます。適正な利益を確保しやすくなるでしょう。
- 顧客からの信頼獲得に繋がる: 高い技術力は、顧客からの厚い信頼を獲得することに繋がり、安定的な受注に繋がります。
慢性的な人手不足で、仕事は途切れない
これは良い事ではないのかもしれませんが、建設業界は、深刻な人手不足が続いており、常に人材が求められています。建設業界で起業する者にとっては明るい未来と言えるでしょう。
特に職人の業務は引く手数多です。起業しても仕事がすぐに得られる事でしょう。
外国人の人材を積極的に雇用する制度を充実させるなど、日本政府も国家的な取り組みを続けており後戻りする事は考えにくい状況です。
仕事がなくなる心配はほとんどありません。 道路や橋梁やトンネルや通信、鉄道など社会や産業の基盤となる各種公共施設また、電気、ガス、水道といった生活基盤となる設備もインフラの新規着工やメンテナンスである公共工事は、今後も増え続けていくでしょう。また民間においても同じく建設に関する投資は増加しています。今後は老朽化した大型、中型のビル、マンションの建て替えとメンテナンスが拡大し、起業後も安定的に仕事を受注できる可能性は非常に高いと言えるでしょう。
- 顧客獲得に奔走する必要がない: 仕事を求めて営業活動に奔走するよりも、技術力向上に集中できます。
- 安定収入で事業計画が立てやすい: 安定した収入が見込めるため、無理のない事業計画を立てることができます。
- 将来的な事業拡大も視野に入る: 人材さえ確保できれば、事業の拡大も夢ではありません。
元いた会社からの仕事でスタートできる
起業しても元いた会社からの仕事を受注できるという点も、建設業界の大きな魅力です。
そのため、いきなり顧客開拓をする必要がなく、スタートアップ直後から順調に仕事を受ける事ができます。
建設業界では、独立後も元請け会社から仕事を受注するケースが一般的です。 これは、独立前に築いた信頼関係や実績が評価されるためです。
営業経験のない人には理解できないかもしれないが、『営業』というのは苦手な人にとってはとても苦痛をともないます。
営業しなくていい環境は、どんなビジネスにとっても理想の環境ともいえるでしょう。建設業において特に職人と呼ばれる人にとっては、仕事の実績そのものが営業活動と言えるかもしれません。
- 独立直後でも仕事に困らない: 顧客開拓に時間を要することがなく、スムーズに事業を軌道に乗せることができます。
- 安定収入で経営基盤を固められる: 安定した収入源を確保することで、経営基盤を早期に確立することができます。
- 無理のないペースで事業を拡大できる: 受注状況を見ながら、自分のペースで事業を拡大していくことができます。
多くの建設会社は、独立した元社員を協力会社として扱い、継続的に仕事を発注します。これは、元社員の技術力や仕事の進め方を熟知しているためです。
例えば、ある中堅建設会社では、独立した元社員に対して、独立後3年間は優先的に仕事を発注する制度を設けています。これにより、独立直後の不安定な時期を乗り越えることができます。
さらに、元の会社からの仕事を通じて実績を積むことで、徐々に他の顧客からの仕事も獲得しやすくなります。このように、建設業界では独立後のスタートアップ期を比較的安定して過ごすことができるのです。
起業 成功 しやすい条件を全て満たしている建設業界の独立
起業家として成功する条件をもう一度記載します。
- 初期費用が低い
- 需要が安定している
- 利益率が高い
- リピーターが多い
- 場所がいらない
これを建設業界にあてはめてみます。
建設業界での起業は、成功の条件を多く満たしています。これらの条件を詳しく見ていきましょう。
初期費用が低い
建設業界での独立は、他の業界と比べて初期費用が低く抑えられることが多いです。これは、大きな設備投資が必要ないためです。
初期費用を抑えられる理由:
- 自宅やレンタルオフィスでの開業が可能
- 高額な設備投資が不要(必要な工具は徐々に揃えていける)
- 人件費を抑えられる(最初は一人親方からスタート可能)
- 広告宣伝費を抑えられる(元の会社からの仕事で開始可能)
例えば、大工として独立する場合、最低限必要な工具セットと軽トラック、そして事務所用のパソコンがあれば開業できます。これらを全て新品で揃えたとしても、100万円程度で済むでしょう。
さらに、前述の通り多くの建設会社が独立支援制度を設けています。これらの制度を利用することで、初期費用をさらに抑えることができます。
低い初期費用は、起業のハードルを大きく下げてくれます。失敗のリスクを最小限に抑えつつ、自分の技術とアイデアを活かしたビジネスにチャレンジできるのです。
利益率が高い
建設業界、特に専門工事業では、他の業界と比べて利益率が高いことが特徴です。これは、技術力や経験が直接的に収益に結びつくためです。
高利益率の要因:
- 技術力に応じた高い報酬
- 材料費以外の経費が比較的少ない
- 人件費の調整が容易(繁忙期は協力会社を活用)
- 固定費を抑えられる(自宅兼事務所での運営が可能)
例えば、左官工事の場合、一般的な利益率は20〜30%程度と言われています。これは、小売業(平均利益率3〜5%)や製造業(平均利益率8〜10%)と比べてもかなり高い水準です。
さらに、技術力が高まるにつれて、より難易度の高い(=単価の高い)仕事を受注できるようになります。これにより、さらなる利益率の向上が期待できます。
高い利益率は、事業の安定性と成長性に直結します。利益を再投資することで、事業規模を拡大したり、新たな分野に進出したりすることも可能になります。
リピーターが多い
建設業界の大きな特徴の一つに、リピーターの多さが挙げられます。一度信頼関係を築いた顧客は、長期的に仕事を発注してくれる傾向があります。
リピーターが多い理由:
- 建物やインフラには定期的なメンテナンスが必要
- 信頼できる業者を変更するリスクを避けたい心理
- 建物の特性を熟知している業者への信頼
- 緊急時の対応の早さへの期待
例えば、ある工場の電気設備工事を請け負った場合、その後の保守点検や修理、増設工事なども同じ業者に依頼されることが多いです。これは、その工場の電気設備の特性を熟知しているためです。
リピーターの多さは、事業の安定性に大きく寄与します。新規顧客の開拓にかかるコストを抑えつつ、安定した収入を得ることができます。さらに、リピーターからの紹介で新規顧客を獲得できる可能性も高まります。
場所がいらない
建設業界での起業の大きな利点の一つは、特定の場所を必要としないことです。これは、初期費用の削減だけでなく、柔軟な働き方を可能にします。
場所が不要な理由:
- 現場が主な仕事場所となる
- 自宅を事務所として使用可能
- 工具や材料は現場に直接配送可能
- オンラインでの見積もりや打ち合わせが一般的に
例えば、塗装業を始める場合、作業は全て顧客の現場で行います。事務作業は自宅で行い、必要な塗料や道具は現場に直接配送してもらうことができます。つまり、高額な家賃を払って事務所や倉庫を借りる必要がないのです。
場所の制約がないことは、起業時のリスクを大きく軽減します。固定費を抑えることができるため、事業が軌道に乗るまでの資金的な余裕が生まれます。また、地域を限定せずに仕事を受注できるため、事業拡大の可能性も広がります。
需要が安定している
建設業界の大きな特徴として、需要の安定性が挙げられます。建物やインフラは私たちの生活に不可欠であり、その需要は景気の変動に左右されにくいのです。
需要が安定している理由:
- 新築需要の継続(住宅、オフィス、工場など)
- 既存建築物の維持修繕需要
- インフラ整備・更新の必要性
- 災害復旧・防災対策工事の需要
- 環境対応や省エネ化のための改修需要
例えば、新築住宅の着工戸数は年間80万戸前後で推移しており、大きな変動はありません。また、既存住宅の平均築年数は約30年と言われており、リフォームや修繕の需要も安定しています。
さらに、日本の社会インフラの多くが高度経済成長期に整備されたものであり、今後更新時期を迎えます。国土交通省の試算によると、2018年度から2047年度までの30年間で、インフラ維持管理・更新費は約570兆円から730兆円に達すると予測されています。
この安定した需要は、起業後の事業継続性を高めます。景気変動の影響を受けにくいため、長期的な視点で事業計画を立てることができます。また、様々な分野の需要があるため、自社の強みを活かせる市場を選択することも可能です。
まとめ
以上、建設業界が起業に適している理由を詳しく見てきました。建設業界への転職は、将来の起業に向けた絶好の準備期間となります。技術を磨き、人脈を広げ、業界の特性を理解することで、成功への道が開かれるのです。
もちろん、起業にはリスクも伴います。しかし、建設業界には起業を成功に導く多くの要素が揃っています。あなたの夢を実現するための第一歩として、建設業界への転職を真剣に検討してみてはいかがでしょうか。
最後に、建設業界での起業を成功させるためのアドバイスをいくつか挙げておきます:
-
- 技術を磨き続ける:技術力は最大の武器です。常に新しい技術や工法を学び続けましょう。
- 人脈を大切にする
建設業界は、起業を目指す人にとって、成功する多くのチャンスが眠っていると言えるでしょう。
自分の技術と努力次第で、高収入と自由な働き方を手に入れることができます。
この記事を参考に、あなたも建設業界での起業を目指してみてはいかがでしょうか?