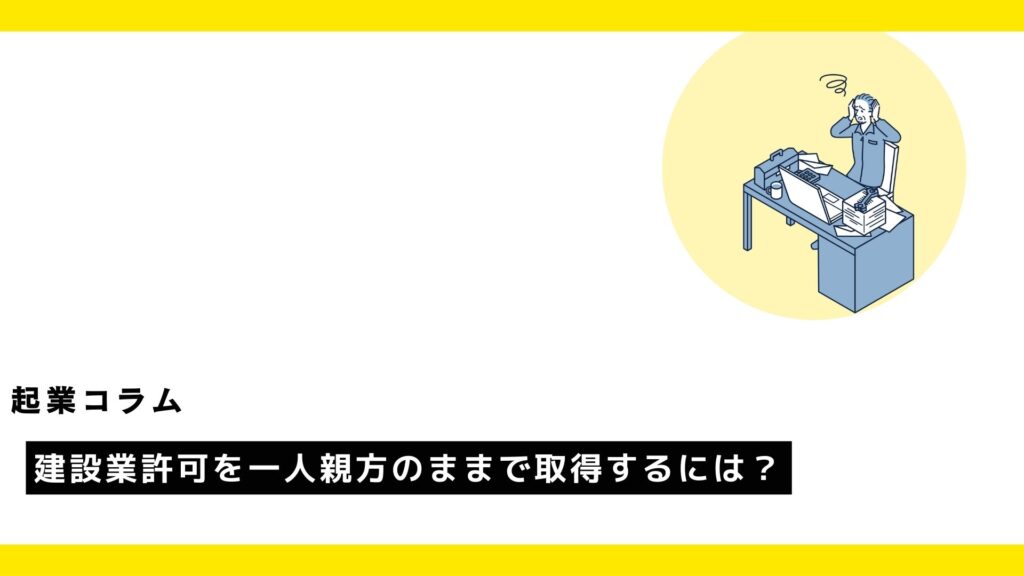建設会社を自ら起業しようと考える際、株式会社か合同会社、どちらにすべきか決められない方もいるのではないでしょうか。
株式会社と合同会社には、それぞれに異なる特徴やメリット・デメリットが存在するため、選択する際は慎重に自分に合ったものを選ぶ必要があります。
この記事では、合同会社で会社を設立するメリットやデメリット、株式会社をおすすめする理由などを詳しく解説します。
ぜひこの記事を株式会社と合同会社への知識を深められる参考にお役立てください。
建設会社の「株式会社」と「合同会社」の違いは?それぞれの特徴を解説
株式会社と合同会社の主な特徴・違いは以下の通りです。
| 株式会社 | 合同会社 | |
| 設立費用 | 約20万円 | 約6万円 |
| 対外的信用 | 高い | 低い |
| 役員の任期 | 最長10年 | なし |
| 税金 | 法人税など (税率25〜35%) |
法人税など (税率25〜35%) |
| 責任 | 有限責任 | 有限責任 |
| 節税 | 幅広く対応可能 | 幅広く対応可能 |
株式会社と合同会社と、日本の法律における2つの主要な会社形態のこと。
株式会社は、株主が株式を所有し、その株式の数に応じて会社の所有権を持つ会社形態です。
株主は、株式を売買することによって、会社の所有権を変更できます。
また、株式会社は、最低資本金が300万円以上必要で、社員の保険や福利厚生など、従業員に対する法定の義務があります。
一方、合同会社は、出資者が持つ権利・義務の内容を自由に決めることが可能です。
出資者は出資額に応じた出資割合によって、合同会社の所有権を持ちます。

また、合同会社は、最低資本金の規定がなく、株式会社と異なり、社員の保険や福利厚生など、法的な義務がありません。

会社の経営者は会社の決定権を持っていますが、代表者がそのまま一人で経営することも可能です。
つまり、株式会社は株主によって所有権が決定され、法律によって社員や従業員の保護が義務付けられています。
一方、合同会社は出資者によって所有権が決定され、自由度が高く、法的な義務が少ない会社形態です。
どちらの会社形態を選ぶかは、企業の目的や状況によって異なります。
以下では、節税面・設立費用・信用度についてさらに詳しく解説します。
-
- 節税面
- 設立費用
- 信用度
節税面
合同会社と株式会社の節税面の大きな違いは、主に課税方式にあります。
合同会社は、所得税と法人税が出資者に直接課税されるのが基本。
つまり、合同会社は出資者によって所有権が決定され、出資者の所得に応じた課税が行われるため、出資者が個人事業主である場合には、個人事業所得として課税されることになります。
また、合同会社は損失を出した場合でも、出資者に分配されることがないため、出資者の所得を相殺することができません。
一方、株式会社は、法人として課税されます。
株式会社は、法人税として利益に対して課税されるため、利益を減らすための経費や損失を相殺することが可能です。
このように、合同会社と株式会社では、課税方式が異なるため、節税方法も違うのがわかります。
設立費用
合同会社と株式会社の設立費用の違いは、主に登記費用や手数料などの面で異なります。
合同会社の設立費用は比較的低く、最低限必要な出資金として10万円以上を用意することで設立が可能です。

また、出資者との契約書作成費用や登記費用なども比較的安価で、合同会社の設立費用全体は30万円から50万円程度で済む場合が多いでしょう。
一方、株式会社の設立費用は、合同会社に比べてかなり高くなるのが一般的。
株式会社の設立には最低限の資本金として300万円が必要であり、この資金を用意するためには出資者が多数必要になることも少なくありません。
また、株式会社は発行株式数に応じて登記費用が高くなるため、設立費用は数百万円から数千万円にもなるケースも。
このように、合同会社と株式会社の設立費用は異なるため、設立予算やビジネスプランに合わせて、どちらの会社形態を選択するかを検討することが大切です。

信用度
合同会社と株式会社は、それぞれ独自の法的枠組みに基づいて設立された企業形態です。
一般的には、株式会社の方が合同会社よりも信用度が高いとされています。
その理由は、株式会社は法的に独立した法人格であると認識され、企業の経営基盤が安定していると考えられているから。
また、株式会社は証券取引所に上場することもできるため、株主に対しても高い透明性を持っていることが信用度向上につながる要因となっています。
一方、合同会社は株主ではなく出資者と呼ばれるメンバーによって所有されるため、株主と企業の責任が分離されていません。
そのため、信用度が低いと考えられることも少なくないでしょう。
ただし、企業の信用度は企業の規模や業界によって異なり、合同会社でも大規模で信用力の高い企業は存在します。

したがって、合同会社と株式会社の信用度については、企業の規模や業界などの要因も踏まえて総合的に判断する必要があります。
建設会社を合同会社で設立するメリット
信用面や透明性を踏まえると、株式会社がおすすめですが、合同会社として設立するメリットもいくつか存在します。
ここからは、建設会社を合同会社で設立する2つのメリットについて解説します。
- 設立費用を抑えられる
- 手続きが簡単
設立費用を抑えられる
建設会社を合同会社で設立するメリットの一つに、設立費用を抑えられることが挙げられます。
合同会社の場合、株式会社と比較して設立に必要な資本金の額が低く設定できるため、設立費用を抑えられるのが魅力です。

さらには、合同会社は会計処理が簡単であるため、会計士や税理士などの専門家の費用を削減することも可能。
さらに、役員報酬や株主に対する配当などの負担も軽くなるため、経費の節約につなげられます。
ただし、合同会社は株主と企業の責任が一体化しているため、経営上の責任を負うメンバーの選定や、経営方針の決定などが重要となります。
また、株式会社に比べて資本金が少ないため、資金調達が難しい場合がある点も理解しておくことが大切です。

手続きが簡単
建設会社を合同会社で設立すると、手続きが簡単であるというのもメリット。
合同会社は、設立時に株式会社に比べて必要な書類が少なく、設立手続きが簡便であるのが特徴です。
例えば、株式会社の場合は定款や発起人名簿、議事録など多くの書類が必要ですが、合同会社の場合はそれらの必要書類が比較的少なく、手続きがスムーズに進むことが期待できます。
ただし、手続きが簡単であることは設立時の利点であり、その後の経営や業務においては経営者やメンバーのスキルや経験が重要となります。
したがって、設立時の手続きの簡便さだけでなく、経営者やメンバーの能力を十分に考慮した上で合同会社の設立を検討することが重要です。
建設会社を合同会社で設立する最大のデメリット
建設会社を合同会社で設立する最大のデメリットは、責任の限定性が法人の範囲内にとどまることです。
つまり、会社が借金をしても、出資者個人の財産は保護されますが、その一方で出資者の資産を借金の返済に充てることができないため、会社の信用が損なわれた場合には、資金調達が困難になる可能性があります。
また、合同会社は株式会社と比較すると株式の売買ができないため、出資者の退社や新しい出資者の参加が困難になることも少なくありません。
さらに、合同会社は、設立や解散手続きが複雑であり、税務処理もややこしくなるケースも。
合同会社で建設会社を設立する場合は、事前にこれらのデメリットを理解した上で、対処法を考慮して設立するようにしましょう。

建設会社を設立するなら株式会社がおすすめの理由
設立費用は合同会社に比べるとどうしても大幅にアップしてしまいますが、世間的な信頼度や金融の借り入れなど、メリットが多くおすすめできるのは株式会社です。
ここからは、建設会社を株式会社で設立する方がおすすめの2つの理由を解説します。
- 資金調達の幅が広い
- 社会的信用が高い
資金調達の幅が広い
建設会社を株式会社で設立すると、資金調達の幅が広がるのがおすすめの理由の一つです。
株式会社は株主からの出資によって資本金を形成するため、多数の投資家からの出資を受け入れることができます。
これにより、資金調達の幅が広がり大規模な事業展開や投資に必要な資金を調達しやすくなるのが魅力です。
また、株式を公開して上場することで、資金調達のみならず企業イメージの向上や知名度の拡大にもつながることがあります。
ただし、株主に対する配当や株価の変動などのリスクもありますので、事前に慎重な検討が必要です。
社会的信用が高い
建設会社を株式会社で設立する最大のメリットは、社会的信用が高まること。
株式会社は法人格を持つため、企業としての責任が明確になり、信頼性がより高まるのが特徴です。
また、株式会社は資本金を有するため、経営者や株主が個人的な責任を負うことなく、企業活動を行うことができます。
そのため、社会的信用が高く大規模なプロジェクトに参加しやすくなるのが強みです。
さらに株式会社の場合は、役員が任期付きで選任されるため、企業の経営が安定化するという利点もあります。
まとめ~合同会社より株式会社の方がおすすめ~
今回は、建設会社を設立するには、株式会社か合同会社のどちらを選ぶべきなのか、それぞれのメリット・デメリット、特徴を踏まえて解説しました。
結論、少し費用はかかりますが、リスクを回避しより信頼度を高められる株式会社がおすすめではありますが、これは事業の内容や目的によっても異なります。
事前に双方をよく理解した上で、自分の将来のビジョンに合う方を慎重に選択することが大切です。
株式会社か合同会社、正しい選択をするためにこの記事を少しでもお役立ていただけると幸いです。