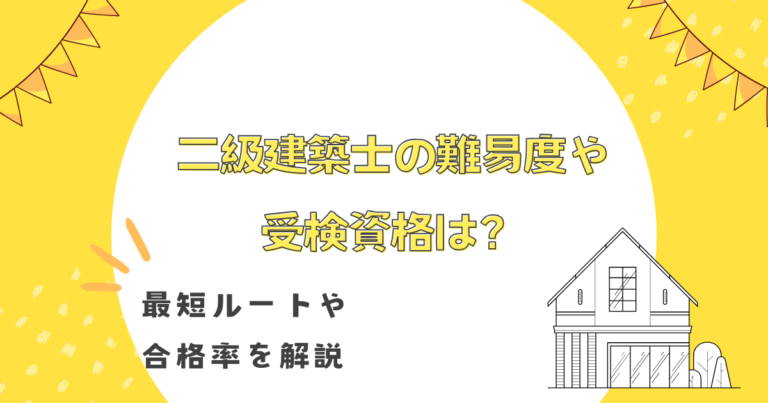二級建築士の資格について
- 二級建築士試験の難易度は高い。過去5年間の合格率はおおむね24%前後
- 二級建築士試験は「学科試験」と「設計製図試験」の2段階。受検資格を得る最短ルートは、指定科目の履修。
「建築士登録状況」によると、令和7年4月1日時点で、796,459人の方が二級建築士の資格を持っています。※
二級建築士試験の受験資格を満たすには、建築関連学部で指定科目を履修するか、7年の実務経験を積むか、建築設備士になってから目指す必要があります。
本記事では、二級建築士試験の受験資格を得るための最短ルートや、二級建築士試験の難易度・合格率、資格取得後の仕事内容などについて、網羅的に解説します。
なお二級建築士の転職には、建築・建設業界に特化した専門の求人サイト「GATEN職」の活用がおすすめです。
二級建築士の資格を持たない人向けの求人も、豊富に掲載しています。
二級建築士資格の難易度
二級建築士は、建築設計や工事監理などの専門業務を担うために必要な国家資格です。
試験の難易度は高く、過去5年間の合格率はおおむね24%前後と、他の建築系資格と比較しても、高い専門性が求められます。
令和6年(2024年)の統計では、全体の合格率が21.8%、学科試験の合格率が39.1%、設計製図試験の合格率が47.0%と報告されています。
試験対策には、学科・実技の両面からの準備が欠かせません。
二級建築士資格の難易度
二級建築士の合格率は約20〜25%
二級建築士試験の合格率は、過去5年間でおおむね24%前後で推移しています。
直近の令和6年度(2024年実施)は、合格率21.8%という結果でした。(※参考:建築技術教育普及センター「試験結果」)
| 二級建築士試験の合格率 | |
|---|---|
| 学科試験の合格率 | 39.1% |
| 設計製図試験の合格率 | 47.0% |
内訳として、学科試験の合格率は39.1%、設計製図試験の合格率は47.0%とされており、いずれも高い専門性が求められます。
データから、二級建築士試験は決して容易ではなく、一定の学習時間と設計スキルを要する国家資格であることが明らかです。
資格取得に向けた、十分な対策が求められます。
二級建築士の合格率が低い理由
二級建築士の合格率が2割台にとどまる背景には、試験構成の複雑さと、実務に即したスキルの要求が挙げられます。
試験は「学科試験」と「設計製図試験」の2段階で構成されており、設計製図試験では次のような実践能力が問われます。(※参考:建築技術教育普及センター「出題科目、出題数等」)
二級建築士の設計製図試験の難しいポイント
- 法令違反のない建築設計を行う法的知識
- 公表された課題に対する計画性と設計力
- 短時間で図面(平面図・立面図など)を完成させる製図技術
- 5時間以内に試験を完遂する時間管理能力
高い専門性と、設計実務への即応性が求められる点が、合格率を押し下げる主因です。
一級建築士と比較した難易度の違い
二級建築士は一級建築士よりも、難易度が低い資格です。
合格率を比較すると、以下の通りとなっており、一級建築士の方が明らかに合格が難しい資格であることがわかります。
| 建築士試験の合格率 | |
|---|---|
| 二級建築士 | 21.8%(令和6年) |
| 一級建築士 | 8.8%(令和6年)※ |
しかしながら、二級建築士も高い専門性が要求される難関資格であることに変わりはありません。
(※参考:令和6年一級建築士試験「設計製図の試験」の合格者を決定~3010人の合格者、26.6%の合格率|国土交通省)
二級建築士資格でできること
二級建築士は、建築士法に基づき、小規模な建築物の設計および工事監理を行う国家資格です。
業務の対象となる建築物には、構造・用途・延べ面積・高さなどによる明確な制限が設けられており、法令に則った範囲内で実務を行う必要があります。
また、令和4年の法改正により、今後は二級建築士が対応できる建築物の規模が3階建て・高さ16m以下へと拡大される見通しです。
このセクションでは、二級建築士の業務範囲、具体的な仕事内容、そして実際に必要とされる職場について、求人データや法令に基づいて解説します。
二級建築士資格でできること
二級建築士が担える業務範囲
二級建築士は、比較的小規模な建築物の設計および、工事監理を行うことができる国家資格です。
一級建築士:全ての構造・規模・用途の建築物について、設計・工事監理を行うことができます。
二級建築士:比較的小規模な建築物についてのみ、設計・工事監理を行うことができます。
木造建築士:より小規模な木造建築物についてのみ、設計・工事監理を行うことができます。
※引用:建築技術教育普及センター「建築士制度の概要」
建築士法により、二級建築士が設計・工事監理を行える対象は、建物の用途・構造・規模に応じて、厳密に制限されています。
例えば、木造建築物については以下の条件で設計・監理が可能です。
二級建築士が設計・工事監理可能な木造建築物
- 高さ13m・軒高9m以下:延べ面積1,000㎡を超える建物も可能(ただし学校や病院などの用途制限あり)
- 高さ13m超または軒高9m超:階数2以下かつ延べ面積300㎡以下
一方、木造以外の構造(RC造・鉄骨造など)の場合は、より厳しい条件が設けられています。
二級建築士が設計・工事監理可能な木造以外の建築物
- 高さ13mかつ軒高9m以下:階数1かつ延べ面積100㎡以下、または階数2以下かつ延べ面積30㎡以下
- 高さ13m超または軒高9m超:階数2以下かつ延べ面積30㎡以下
(※参考:愛媛県庁【建築士の業務範囲】 (建築士法第3条、第3条の2、第3条の3))
また、改正建築士法(令和4年6月17日公布)により、二級建築士の業務範囲は3年以内に見直しされる見込みです。(※参考:建築技術教育普及センター「建築士制度の概要」)
改正後は「階数3以下、かつ高さ16m以下」までの木造建築物を取り扱えるようになり、対象となる建築物の幅が広がります。(※参考:令和4年改正 建築基準法について – 住宅 – 国土交通省)
二級建築士の主な仕事内容
二級建築士の仕事内容は、大きく分けて設計業務と工事監理業務に分類されます。(※参考:建築技術教育普及センター「建築士制度の概要」)
一定の建築物の設計・工事監理業務は、建築士法で「建築士でなければ行ってはならない」と規定されており、法的に業務独占が認められています。
二級建築士が携わる主な仕事内容
- 設計業務:建築基準法や関連法令に基づき、建物の設計図書を作成し、委託者への説明責任も担います。作成した図面には建築士本(※参考:建築技術教育普及センター「建築士制度の概要」)人の記名が必要です。
- 工事監理業務:設計図どおりに工事が行われているかを確認し、相違があれば施工者へ是正指示を出します。工事完了後には、建築主へ書面で報告を行います。
- その他:建築関連の契約手続き、法令対応、現場指導、監督なども含まれます。
二級建築士が必要とされる職場
二級建築士の資格保有者は、以下のような多様な職場で需要があります。(※参考:求人ボックス)
二級建築士が携わる主な仕事内容
- リフォーム会社:リフォーム分野は特に求人が多く、設計・現場監理・営業技術支援などで活躍します。福祉用リフォームやコープ組合向け住宅改修など、専門性の高い案件もあります。
- 工務店・建設会社:戸建て住宅や中規模建築物を手掛ける企業において、施工管理や設計・見積業務に従事するケースが一般的です。
- 建築設計事務所:設計補助や小規模建築物の主担当としての業務が多く、図面作成や構造提案も担当します。
- 不動産・住宅関連企業:住宅性能評価・既存住宅の調査・建築相談・リノベーション提案といった業務において資格が活用されます。
- 専門業務企業(鉄骨・建材加工など):資格保持が優遇条件とされ、加工図作成や仕様確認などに従事する場合もあります。
求人情報においては、住宅の設計・リフォーム設計・施工管理・メンテナンス提案などの分野で二級建築士の需要が高く、次のような実務で活用されています。(※参考:求人ボックス)
二級建築士の求人例
- 戸建て住宅のリフォーム設計
- 福祉施設向け改修の図面作成・提案
- 注文住宅の設計・現場監理
- 瑕疵担保保険対応の劣化診断・報告
- 公共工事における図面調整・工事管理
上記の通り、二級建築士は建築業界全体の幅広い分野で必要とされている資格です。
お仕事を検索
二級建築士資格の試験内容
二級建築士試験は、建築に関する専門知識と実技能力の両方を評価する国家試験です。
試験は「学科試験」と「設計製図試験」の2段階に分かれ、出題内容や評価基準は建築士法および施行規則に基づいて定められています。
また、試験の実施は公益財団法人建築技術教育普及センターによって行われており、受験申込から合格発表、免許登録に関する情報も一元的に管理されています。
以下では、学科試験・設計製図試験の具体的内容と、申込方法・日程などについて詳しく解説します。
二級建築士資格の試験内容
学科試験の内容
二級建築士資格の学科試験では、建築に関する基礎知識および法令遵守能力を判定するため、以下の4科目が出題されます。(※参考:建築技術教育普及センター|出題科目、出題数等、令和7年 二級建築士試験・木造建築士試験 受験要領)
| 科目 | 学科Ⅰ:建築計画/学科Ⅱ:建築法規/学科Ⅲ:建築構造/学科Ⅳ:建築施工 |
|---|---|
| 出題数 | 各25問(計100問) |
| 出題形式 | 五肢択一式(マークシート方式) |
| 試験時間 | 前半3時間(学科Ⅰ・Ⅱ)+後半3時間(学科Ⅲ・Ⅳ) |
| 携行品 | 法令集(学科Ⅱのみ可/書き込み制限あり)、筆記用具、時計(アラーム不可)など |
設計製図試験の内容
二級建築士資格の設計製図試験では、事前に公表された課題に沿って建築計画を行い、設計図書を5時間以内に作成する能力が問われます。(※参考:建築技術教育普及センター「建築士制度の概要」、令和7年 二級建築士試験・木造建築士試験 受験要領)(※参考:日建学院「2024年度 受験合格対策 2級建築士 集中ゼミWebコース」)
| 主な出題内容 | 配置図、平面図、立面図、断面図、面積表、仕上表、計画の要点 等 |
|---|---|
| 構造形式 | 木造または非木造のいずれか(年度により異なる) |
| 試験時間 | 1課題5時間 |
| 携行品 | 製図板(45cm×60cm以内)、T定規、三角定規、型板、円定規、コンパス、消し板など |
試験スケジュール・申込方法
二級建築士の資格試験は、建築技術教育普及センターが毎年実施しています。
2025年度の試験日程や申込方法は、以下の通りです。(※参考:建築技術教育普及センター令和7年 二級建築士試験・木造建築士試験 受験要領)
二級建築士資格の試験内容
- 学科試験:2025年7月6日(日)
- 設計製図試験:2025年9月14日(日)
- 設計製図課題公表:6月18日(水)
| 申込方法 | 原則インターネット(4月1日~4月14日) |
|---|---|
| 受験手数料 | 18,500円(非課税)+事務手数料(クレカ306円、コンビニ225円) |
| 受験票発行 | 学科:6月20日頃/製図:8月25日頃(マイページからDL) |
| 合格発表 | 学科:8月25日/製図:12月2日(予定) |
二級建築士試験の受験資格を得る方法
二級建築士試験を受験するには、建築士法および関連法令に基づいた、受験資格要件を満たす必要があります。
受験資格要件を満たす主なルートは「指定科目の履修」「建築実務の経験」「建築設備士資格の取得」の3つです。
それぞれの条件には適用範囲や例外規定があるため、自身の学歴や職歴に応じた判断が求められます。
二級建築士試験を受験するルート
最短ルートは指定科目の履修
二級建築士の受験資格を最短で取得できるルートは、国土交通大臣の指定する建築に関する「指定科目」を所定の学校で修得し、卒業することです。(参考:建築技術教育普及センター「受験資格」)
指定科目の履修で二級建築士の受験資格を取得する方法
- 大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・専修学校・職業訓練校などに在籍
- 必要な単位を修得する
- 指定科目を修了した場合、実務経験なし(0年)で受験可能
- 学校種別により必要単位数や卒業条件が異なる
実務経験を積まずに受験できるため、最短かつ標準的な取得ルートとして、多くの受験者に利用されています。
7年間の実務経験を積む
建築に関する学歴がない場合は、所定の建築実務を7年以上継続して従事することにより、二級建築士の受験資格を得ることが可能です。
必要な実務経験は建築士法および国土交通省令により定められており、単なる労務や事務職では認められません。
令和2年3月1日以降に開始された実務の例は、次の通りです。
実務経験として認められる業務
- 建築物の設計・図面作成・積算・施工計画の策定
- 工事監理・現場での是正指示・報告書作成
- 性能評価、耐震診断、維持保全計画策定
- 建築行政・確認審査・都市計画業務
- 大学院におけるインターンシップなど、実務に準ずる教育活動
なお、「写図工」「一般事務」「会計処理」などの業務は実務経験として認定されません。
(※参考:建築士資格に係る実務経験の対象実務の例示表 (令和 2 年 3 月 1 日以降の実務) – 建築技術教育普及センター)
建築設備士になる
建築設備士の資格を有している者は、実務経験なし(0年)で二級建築士試験の受験資格を取得可能です。(参考:建築技術教育普及センター「受験資格」)
ポイント
- 建築設備士は、建築物の設備設計に特化した国家資格
- 国土交通大臣が定める特例措置として、即時に受験資格を得られるルート
このルートは、すでに設備設計分野で専門性を有している技術者が、建築士資格を追加で取得する際に用いられます。
二級建築士には受験資格があり合格率は低い
二級建築士には受験資格があり、合格率は低いです。
しかし二級建築士の資格を取得すると、さまざまなメリットがあります。
二級建築士の資格を取るメリット
- 転職先の幅が広がる
- 顧客や転職先から信用を得られる
- 資格手当がもらえる
- キャリアの支えになる
- 一級建築士を受験できるようになる
二級建築士の資格を活かして建築業界で働きたい方や、これから二級建築士を目指したい方には、求人サイト「GATEN職」がおすすめです。

| GATEN職の詳細 | |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アール・エム |
| 対応地域 | 全国 |
| 求人数 | 7,446件(2026年1月時点) |
| 業種 | 建設業界中心 |
| 未経験 | ○ |
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、アルバイト、業務委託 |
| 特徴 | 会員登録なしで求人に応募可能 |
| 住所 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング5F |
| 厚生労働省事業者届出番号 | 51-募-000945 |
- GATEN職の特徴建築・建設業界の求人を掲載している
- 建築業界の求人が7,000件以上掲載されている
- 正社員からアルバイトまで様々な雇用形態の求人を見つけられる
- 希望条件を詳細まで絞って検索できる
- 動画から求人を探すことができる
GATEN職は、建築・建設業界の求人を取り扱っているサービスです。
建築業界の7000件以上の求人が掲載されており、希望条件を詳細に絞り込んで検索することが可能です。
求人ごとに写真や動画コンテンツも掲載されており、転職後の働き方を容易に想像できます。
また、正社員からアルバイトまで、幅広い雇用形態の求人があります。
二級建築士の資格を活かして建築業界で働きたい方や、これから二級建築士を目指したい方は、ぜひ活用してください。